
「我が家の愛犬は健康だから動物病院いらず!」そう思っている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
しかし、健康に長生きしてもらうためにも、健康診断を定期的に受けることはとても大切なのです。
健康診断といっても、内容はその子の年齢や体質によってさまざま。
愛犬にとって有意義な健康診断にするために、飼い主さんが知っておくべきポイントをお伝えします。
犬に健康診断は必要?受けるメリット

飼い主さんから「病気になった時だけ受診をすればよいのでは?」「うちの子は元気だから健康診断は必要ないのでは?」といった声を耳にすることがあります。
しかし、健康診断は愛犬が健康に長生きするためにとても大切な役割があります。では、どのようなメリットがあるのでしょうか?
早期発見・早期治療につながる
健康診断にはさまざまな種類があり、受けることで病気の早期発見や早期治療が可能というメリットがあります。
症状が現れてから気づく場合にはトラブルが進行していて、治療の選択肢が狭まったり予後が悪くなったりする可能性があるため、早期発見・早期治療はとても大切です。
発見が遅れることで死に至る可能性も高まり、飼い主さんの後悔につながる場合もあります。
目立った変化が見られなくても定期的な健康診断は、愛犬を守る大切な習慣になります。
健康診断で生活習慣の見直しができる
犬も成長や加齢とともに体に変化が見られるようになります。ずっと同じ生活を送ることが、愛犬の体に負担をかけてしまう場合もあるでしょう。
健康診断の結果を正しく分析することで、見直すべき生活習慣が見えてきます。
特に中高齢に差し掛かった犬は、体の器官の機能低下が始まる時期でもあり、飼い主さんが変化に気付きづらい場合もあります。
健康診断でより早く老化のサインを把握し負担の少ない生活に変えることで、健康で長生きできる可能性が高まるでしょう。
健康診断の主な検査項目

ここからは具体的な健康診断の項目をご紹介します。
基本検査(身体検査・問診・視診・触診・聴診など)
基本検査は一番簡易な検査であり、犬にとって負担もかかりにくく、ワクチン接種などの予防のタイミングで行うことが一般的です。
特に成長期など変化が見られやすい時期は、こまめに受けることで飼い主さんも気づかなかった変化に気づける場合があります。
生活の見直しや注意すべき点の発見などにつながる可能性もあるので、最低限行うべき項目ともいえるでしょう。
子犬期の社会化の一環として、飼い主さん以外の人に慣らすための練習としても、こまめな受診は有意義なものになります。
血液・尿・便検査
血液検査にもさまざまな種類があり、赤血球や白血球の変化を把握するための全血検査、体内の器官の変化を把握するための血液生化学検査と呼ばれる検査が一般的です。
- 全血検査:脱水や貧血の有無、炎症や腫瘍性変化による白血球の増加などを把握することが可能
- 血液生化学検査:多数の項目があり、知りたい器官の変化によって選択することが可能
健康診断では一般的に把握しておくべき項目がセットになっている場合があるため、健康診断用のまとまったものを選択できると安心でしょう。
また、内分泌の変化を調べる検査や血液の凝固の異常の有無などを調べる特殊検査もありますが、気になる症状や変化によって選択する場合が多いです。
尿や便検査は、愛犬に負担をかけずに行える検査の一つといえます。泌尿器系トラブルを持っている子や便の状態が不安定な子は、こまめに受けておくと安心です。
画像検査(レントゲン・超音波など)
血液検査や尿、便検査などで把握できないことを確認できるのが画像検査です。
レントゲン検査では骨格系の変化や呼吸器の状態、心臓の肥大の程度、消化器の状態などが確認できます。
中高齢で変化に気づきにくい体の中の状態も把握できるため、とても有意義な項目といえるでしょう。
超音波検査も、臓器の過形成や内腔の様子、腫瘍性病変の有無、心臓の動きについて確認できるため、症状が現れる前に変化に気づける可能性があります。
また、変化に気付くことで、健診の頻度や日常生活での注意点の発見につながるため、血液検査や一般検査に加えて受けておくと安心です。
ペットの健康診断は、予防医療や健康診断の普及を目指す獣医師団体「Team HOPE」も積極的に取り組んでいます。
Team HOPEでは、病気を見逃さないために、問診・視診・触診・聴診・血液検査・尿検査・レントゲンの7つの検査を受診いただくことをおすすめしています。
Team HOPEが作成した、健康診断のシミュレーション動画もぜひご覧ください。実際の健康診断の流れが詳しく解説されています。
健康診断はいつから必要?頻度はどのくらい?

健康診断にはさまざまな種類があり、必要な検査項目や頻度は月齢によっても異なります。
ここからは、ライフステージごとに押さえておきたい頻度や項目を解説します。
子犬期
家庭にお迎えしたばかりの子犬は、先天的な疾患を持っていない限り大きなトラブルを抱えている可能性は低いでしょう。
ただし、成長期は体の変化が大きいため、検査によっては正確な値が把握しにくくなる項目もあります。
まずは、一般的な健診をこまめに受け、成長が順調かを確認することや動物病院に慣らすことを優先するとよいでしょう。
- 体重測定
- 触診
- 視診
- 聴診
これらの項目は、犬に大きな負担がないため、1か月に1度などこまめに行うことをおすすめします。
健診では、飼い主さんが気づかなかったポイントを専門家の視点でアドバイスしてもらえる可能性も高く、日常生活で困っていることを相談できる場にもなるでしょう。
成犬期
成犬期は体の成長や器官の発達も完了し、大きな問題も起きにくい月齢です。
成犬期の健康診断は、健康な時の愛犬の体の傾向を把握するためにも、症状が見られなくても受けておくと安心でしょう。
健康時の状態が把握できていると、トラブルが起きた際に小さな変化でも数値の比較ができ、早期発見・治療を行うことが可能です。
さらに、愛犬の器官ごとの機能低下や数値の変動傾向を知ることで、生活習慣を見直せ、病気を未然に防ぐこともできるでしょう。
子犬期のような最低限の項目と併せて、1年に1回程度の血液検査がおすすめです。
体内の器官の状態を把握できる一般的な項目を行うことで、全身状態の把握につながります。
シニア期
犬種差や個体差がありますが、大型犬であれば大体5歳以降、小〜中型犬であれば7歳以降が中年〜シニア期に差し掛かるとされています。
中年〜シニア期は、体の機能低下が起こり始め変化が見られやすくなる時期でもあります。健康診断の内容も、より項目を増やせると安心です。
レントゲンや超音波検査をしておくと、骨格や呼吸器の変化、腫瘍性病変の疑いの有無など血液検査ではわかり得なかった部分も見えてくるため、より早期にトラブルを発見できます。
また、内分泌疾患の可能性なども疑わしい場合は、一般的な血液生化学検査に加えて、内分泌の検査なども行うと安心でしょう。
かかりつけ医と相談して、日常生活の中で気になる変化や犬種特有のなりやすい疾患などに合わせて項目を決定することをおすすめします。
また犬は1年で4〜6歳のスピードで歳をとるため、1年ごとの健康診断では変化の始まるタイミングが把握しづらくなります。
愛犬の全身状態によりますが、シニア期は長くても半年に1度くらいの間隔で、こまめに受けておくと安心です。
大型犬・小型犬での頻度の違い

大型犬は、腫瘍性病変の形成や運動器系のトラブルが起こりやすい傾向があります。
一般的な血液検査を行うことに加え、レントゲン検査や超音波検査などの画像診断の追加で、より変化を発見しやすくなるでしょう。
また、大型犬は小〜中型犬に比べて寿命も短く加齢も早く始まります。若齢のうちから最低でも年に1回は健康診断を受けましょう。
変化に気づいた場合は、年2回の健診に切り替えられるよう、日常生活での観察も欠かさないことが大切です。
犬の健康診断にかかる費用の目安
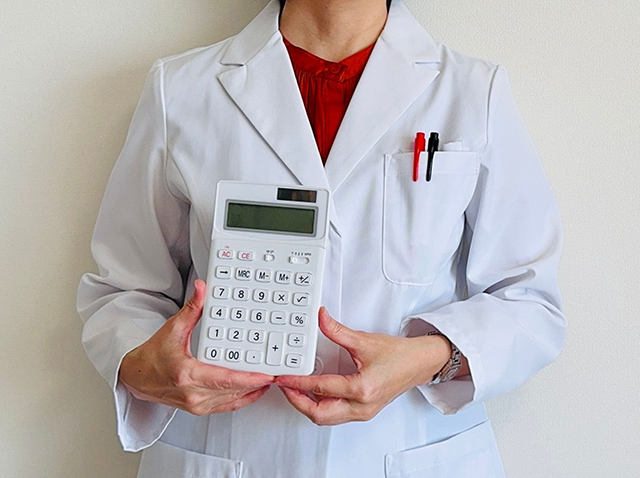
健康診断の費用は動物病院や項目によってさまざまですが、一般検査などは5000円程で行える場合が多いです。
血液検査や画像診断などは項目や見る部位の数によって費用も異なり、1万円〜数万円になる場合もあります。
特にレントゲン検査などは、見る部位の大きさによって撮影するフィルムも異なるため、サイズによって費用は異なります。
そのため、大型犬は小型犬よりも大きめのフィルムを使用するケースもあり、費用が増えることも多いです。
また、一般的な画像診断に加えてCTやMRIなどの画像診断も健康診断として行う場合、麻酔下でする必要性があるため、麻酔管理の費用が追加される場合もあります。
その場合は10万円程度になってしまうことも。事前にかかりつけの先生に受ける予定の健康診断の項目と費用の確認をしておくと安心です。
犬の健康診断を受けるときの流れ

健康診断をより有意義なものにするために、当日受けることを決めるのではなく、きちんと事前に受診を決めて準備をすることがおすすめです。
健康診断の項目によって異なりますが、どのような流れで行われるのかを知っていますか?
獣医師の先生に任せるだけでなく、愛犬がどのような検査を受けるのかを把握することはとても大切です。
事前に準備しておきたいこと(食事制限・尿・便検査など)
健康診断の予約をとった後に、確認や準備をしておいたほうがよいことがいくつかあります。
- 絶食のタイミング
- 尿や便の保存方法
- どのような処置を行うのかを把握
血液検査をするうえで、食後に計測をすると食事の影響を受けてしまい、正確に計測できなくなる項目があります。
そのため、検査前には約10時間くらいの絶食が望ましいとされています。
ただし、脂質代謝が苦手な子や、今までの検査で正確な値が測定できなかったケースがある場合などは、さらに絶食時間を指定される場合もあるため、愛犬に適した絶食時間を確認しておきましょう。
尿や便の保存方法も、より正確な検査を行うために把握しておく必要があります。
検査の時期や時間帯、愛犬の排せつのタイミングで長時間の保存が必要になる場合は、常温・冷蔵など適切な保存方法を事前に聞いておきましょう。
また、処置によっては愛犬が苦手とすることを行う必要がある場合もあります。
超音波検査などは特定の姿勢での保定が必要な場合もあり、抱っこや触られることが苦手な子の場合、事前に伝えておく方がよいかもしれません。
健康診断による負担の軽減や内容の見直しにもつながるため、愛犬の受ける検査項目を把握しておきましょう。
当日の流れ(受付~検査~説明)
健康診断の受付から検査の実施、説明、検査結果までかかる時間は内容によって幅があります。
超音波検査や麻酔をかけたうえでMRIやCT検査などを行う場合は、半日や1日かかることもあるでしょう。
長時間の場合は、病院に愛犬を預けて指定された時間に飼い主さんが戻ってくるという場合もあります。予約の際に当日の所要時間の目安を確認しておきましょう。
また検査結果も即日わかる場合や後日受診をして聞く場合など、内容や病院によってさまざまなので、かかりつけの動物病院はどのようなスタイルなのか、あらかじめ把握していると安心です。
健康診断で異常が見つかったら

異常が見つかって動揺してしまう飼い主さんもいるかもしれません。
異常があることは心配なことですが、健康診断で発見できると、進行する前に予防や治療ができる可能性が高くなります。その結果、愛犬への負担を少なくした状態で治療に移行できる場合もあります。
また、早期であれば治療の選択肢が広がる場合もあり、飼い主さんの希望や愛犬の性格なども考慮した治療が受けられるでしょう。
また、生活の見直しによって予後が良くなる可能性もあります。
早期に異常を発見できたら、早期治療を行い愛犬と過ごせる時間がより長くなるよう、飼い主さんもサポートしてあげましょう。
治療について、不明点が多いと不安なことも増えてしまうでしょう。以下のような記事もぜひ参考にしてみてください。
健康診断を受けて愛犬の長生きをサポートしよう

愛犬が健康に長生きするというのは、飼い主さんの願いでしょう。愛犬の健康には、飼い主さんの理解とサポートが欠かせません。
動物病院は病気の診察・治療だけではなく、ワクチンや健康診断、日常のケアなどを通じてペットと飼い主が一緒に安心して長く暮らせるようサポートしてくれる病院を選びましょう。
また、健康診断を受けることだけで満足せず、結果を正しく理解し、愛犬との生活で見直すべき点を早期に知ることはとても有意義です。
愛犬の状態を正しく把握し、専門家であるかかりつけの獣医師の先生と二人三脚で愛犬の生活をサポートできると良いですね。
ペットの健康診断を推進する獣医師団体「Team HOPE」では「Team HOPE健康診断キャンペーン」を実施しています。
期間は、2025年10月13日(月・祝)を含む10月1日(水)〜12月31日(水)の3ヶ月間。
健康診断はこの期間以外にも通年で行っていますが、愛犬の健康のためにもぜひこの機会に受診してみてください。
※病院によって実施の有無やキャンペーン期間が異なる場合がありますので、各病院へお問合せください。

獣医師。動物病院、会員制電話相談動物病院などを経て動物病院を開院。
興味がある分野は、皮膚科や産科、小児科。12頭の犬、3匹の病院猫と生活する。












