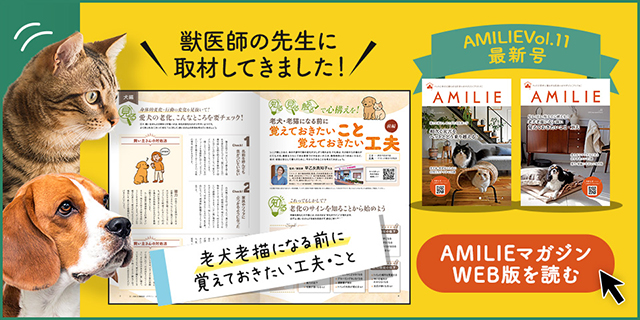シニア期に入ると、体の不調や行動の変化が少しずつ現れます。でも実は、その前からの備えが とても大切。
健康なうちにできる習慣づけや住まいの工夫、動物病院とのつきあい方など、 老猫と安心して暮らすために、今からできることを考えてみましょう。

監修/獣医師 早乙女真智子先生
「マリーナ 街の動物病院」院長。日本獣医畜産大学 卒業。2006年に「マリーナ 街の動物病院」を開院 し、地元密着の動物病院として地域の1次診療を担っている。趣味は登山とバレーボール。
猫の老化のサインを知ることから始めよう
年齢を重ねた犬や猫には、さまざまな“老化のサイン”が現れます。 まずは、飼い主さんが兆候を見逃さず、適切に寄り添うことが大切です。
身体的変化
- 筋肉量の低下
- 聴力の低下
- 視力の低下
- 毛艶が悪くなるなど
行動の変化
- 高いところに上らなくなる
- グルーミングをしなくなる
- 運動量が減る
- トイレの失敗が増えるなど
認知機能の低下
- トイレの場所を間違える
- 今いる場所がわからなくなる
- 反応が鈍くなるなど
愛猫の身体的変化・行動の変化、どこに注意すればよい?

普段から自由気ままな猫。老化のきざしも「今はそんな気分かな?」と捉えてしまいがちです。気がついた時には...とならないように、愛猫がシニア期になる前から少しずつチェックを。
Check①寝てばかりいる
基本的に猫は元気でも老化していても寝ていることが多いため 、飼い主さんが変化に気が付きにくい傾向があります。気がついた時には、老化による病気が進行していることも。
よく観察すると、うんちが固くなった、吐くことが増えた、食べる量が減ったといった変化で異常に気がつくことがあります。また、口の中のニオイが独特になることも。
Check②爪とぎをしなくなった
興味低下という可能性もありますが、関節炎による手の痛みで爪とぎをしなくなるパターンが多いようです。
猫の爪は通常、爪とぎによって古い層が剥がれていきますが、爪とぎをしなくなると何層も重なったままになります。
以前は鋭かった爪が分厚くなってきたり、丸くなってきたりしたら、爪とぎをしていない可能性があります。
飼い主さんの対処法
適切な爪とぎができないまま放置してしまうと、巻き爪による肉球の刺傷・感染症や、床で滑りやすくなり転倒するリスクが高まります。
飼い主さんは肉球に爪が刺さるほど伸びてないかを常にチェックしてください。厚くなった爪は切るのが大変になるので、獣医師さんに相談して切ってもらうのも手です。
Check③高いところに上らなくなった
老化の進んだ猫が、今まで上っていたキャットタワーに興味を示さなくなることがあります。
爪とぎと同様、手足に関節炎が起こっているため、上るときや着地などに痛みを感じて嫌がっている可能性がありま す。
また、視力の低下により足元がよく見えず、落下への不安から、高所へ上がることを躊躇する猫も。
飼い主さんの対処法
猫は本能的に上下運動が必要な動物なので、歳をとっても完全に平面で暮らすことは避けたほうがよいでしょう。
ただし、猫自身が上れる高さが限られるので、たとえば家の中に階段上のラックを設置するなど、垂直ではなく斜めに上れる段差を作ってあげれば、老猫になっても身体を動かすことができます。
愛猫の年齢や体格にあわせて調整できるキャットタワーやステップなども用意しておくと便利ですね。
〈AMILIEチャンネルで動画公開中!〉
動画では、老化のサインや暮らしの工夫、注意点についてより深掘りしています。タメになる情報満載ですのでぜひチェックしてみてくださいね!
老猫になる前に、飼い主さんに気づいてほしいこと

「いつもの様子」と「スキンシップ」を心がけて
シニア期に入る前の心がけが、その後の暮らしをより快適にしてくれます。 毎日の「いつも」と触れ合いを大切にすることが、小さな変化に気づく第一歩に。
これからも心地よく過ごすために、飼い主さんにできることを早乙女先生に伺いました。
飼い主さんにできること、具体的なポイントとは…?
①愛猫の「いつもと違う」は、獣医師も知りたい
②撫でる時間が、病気のサインに気づくきっかけに
詳しくは「AMILIE マガジン Vol.11」で解説しています!無料で読めますので、ぜひ下のバナーからチェックしてみてくださいね♪
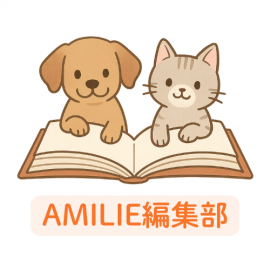
ペット愛好家のみなさまに住まいの情報を日々発信中!